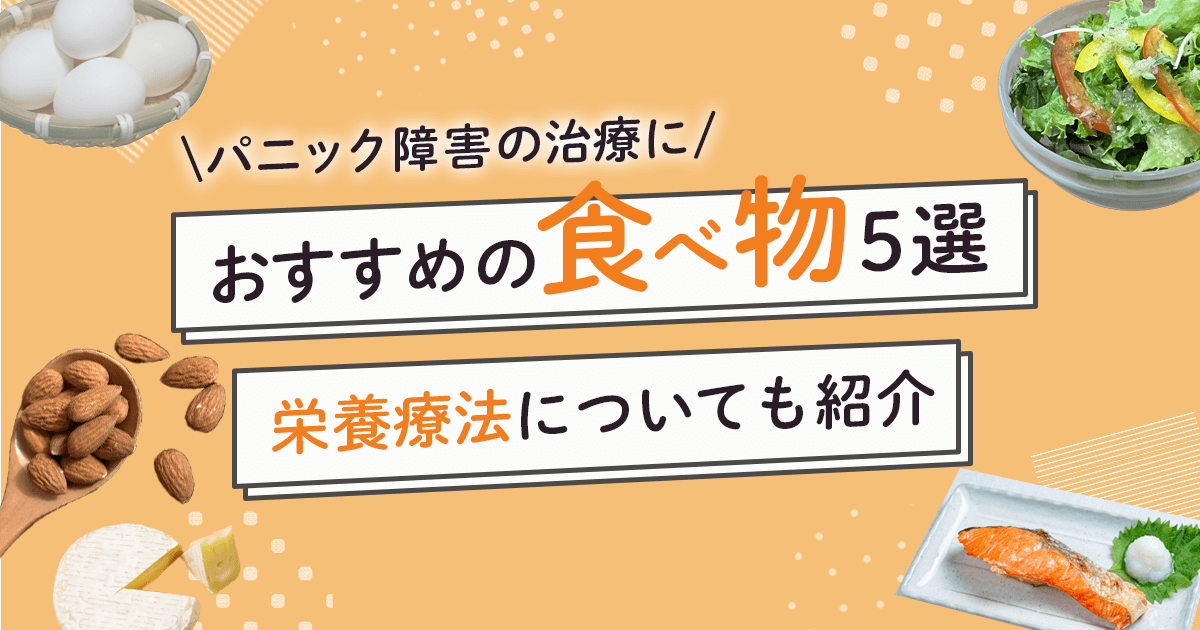この記事では対処法も交え、パニック障害で外食できない理由を解説します。
- 外食への不安・恐怖が和らぐ5つの解消法がわかる
- パニック障害を持つ人が外食を誘われた時の対処法がわかる
- パニック障害を持つ人が外食できるようになる訓練法がわかる
なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。
「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。
「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。
「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。
本記事を音声で聴く
パニック障害で外食できない6つの原因

さっそくパニック障害で外食できない主な原因を、6つにまとめて紹介します。
原因1:過度な緊張の発生
周囲の目線が気になることで生じる過度な緊張状態は、パニック障害で外食できない原因の1つです。
過度な緊張状態は、 危険から身を守ろうとする時に脳や自律神経が活発的に働く反応です。パニック障害の人は危険な状態でなくても「危険だ」と過剰に認識してしまい発生します。
過度な緊張状態がつづくと、「食欲不振・のどの詰まり・吐き気」の症状が発生し外食ができなくなるのです。
原因2:食べるのが怖い
食べること自体が怖くなる点も、パニック障害で外食できない原因の1つです。
「食べ物がうまく飲み込めない」と感じ、食べること自体が怖くなります。「このまま息ができなくなったらどうしよう…」と不安になるのです。
そして、食べること自体に強い抵抗感を感じます。1度でも食べること自体が怖くなると、トラウマを抱え食べ物を口にできなくなるのです。
原因3:外出自体が怖い
外出自体が怖くなる点も、パニック障害で外食できない原因の1つです。
外出時は、常に知らない人が周囲にいます。そのため、発作が起きた時に「変に思われたらどうしよう」と周りを過剰に気にしてしまうのです。
また、「迷惑をかけたくない」気持ちが強くなり外出自体を避けるようになります。パニック障害を持つ人は「外に出なければ安心できる」と思い、回避行動が強化されるのです。
原因4:外食中に症状が起きることへの恐怖
外食中に症状が起きることへの恐怖も、パニック障害で外食できない原因の1つです。
パニック障害も持つ人は、いつ症状が起きるか常に不安を感じています。そのため、外食中に症状が発生した場合を想定してしまい外食ができなくなるのです。
苦手意識から外食を控えるようになります。
原因5:店内から逃げられない恐怖
店内から逃げられない恐怖を感じてしまう点も、パニック障害で外食できない原因の1つです。
パニック障害を持つ人は、「すぐに外に出られないのでは?」と店内から逃げられない恐怖を感じます。店内での食事は注文したら食べ終わるまで帰れません。
強制力が、パニック障害を持つ人にとって外食できない原因になるのです。
原因6:過去のトラウマによる恐怖
過去のトラウマによる恐怖がある場合も、パニック障害で外食できない原因の1つです。
「前にあのレストランで発作が起きた」という経験があると、「また起きるかもしれない」と強く意識します。その結果、外食に対する恐怖心が増します。
パニック障害を持つ人は、自宅で食事をした方が恐怖を感じず楽なのです。
パニック障害の症状の特徴は、予期されない「パニック発作」を繰り返すことであり、死を感じるような恐怖感に襲われ、動悸やめまい、窒息感などの症状が出現します。「また発作が起きるのではないか」という不安を常に感じる「予期不安」もパニック障害の症状の特徴で、予期不安がエスカレートすると仕事や日常生活にも支障をきたします。
引用:PTSDとパニック障害の関係性
トラウマがあると、「やっぱり怖い」という気持ちが消えず外食へのハードルが高くなり続けます。
根本的なパニック障害の発症原因をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

外食への不安・恐怖が和らぐ5つの解消法

原因をおさえたところで、ここからは外食への不安・恐怖が和らぐ解消法を5つにまとめて解説します。
実際に外食する予定がある方は参考にしてください。
解消法1:「途中で帰っても良い」と言い聞かせる
「途中で帰っても良い」と自分に言い聞かせることで、パニック障害による心理的な負担を減らせます。
外食へ恐怖を感じる理由の1つは、「最後までいなければならない」という負担です。思い込みが強いほど、外食がストレスになります。
たとえば、「もし途中で具合が悪くなったらすぐに店を出ても良い」と決めるだけで気持ちが軽くなるのです。遠慮せず店員さんに「体調が悪いので帰ります」と声をかけましょう。店員さんも、不振に思うことはなく事情を把握してくれます。
上記を含め、言い聞かせることで気持ちが安心する言葉をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

解消法2:家族や信頼できる友人と一緒にいく
家族や信頼できる友人と一緒にいくことにより、パニック障害から落ち着いて食事ができます。
パニック障害を持つ人にとって、「1人で対処しなければいけない」という状況は大きな不安要素です。家族や信頼できる友人がそばにいるだけで安心感が生まれます。
たとえば、事前に「もし発作が出たら帰らせてほしい」と伝えることにより外食への不安を和らげます。家族や信頼できる友人なら、変に思われることはないので臆せず伝えましょう。
解消法3:道順を頭に入れておく
外食するお店への道順を頭に入れておくだけで、外出時のパニック障害による不安が和らぎます。
「どこに向かっているのかわからない」という状況は、パニック障害の不安を加速させる原因になるのです。特に電車やバスを使う場合、余計に神経を使うためストレスにつながります。
たとえば、グーグルマップで1度道順を確認するだけでパニック障害の不安が軽減されます。事前に「どの駅で降りるか」「お店の入り口はどこか」などを把握しておくと、気持ちに余裕が生まれます。
実際に、道順のメモを持つことが有効的です。
解消法4:症状が出た時の対処法を練習しておく
「発作が起きても大丈夫」と思えるよう、パニック障害の症状が出た時の対処法を練習しておくと安心です。
パニック障害による予期不安が強い場合、「発作が起きたらどうしよう」と考え結果的に発作が起こります。パニック障害の対処法を知っていれば、「もしもの時も落ち着ける」という自信につながります。
たとえば、外出前に深呼吸やリラックス法を練習しておくと発作が起きそうなときにすぐに対処できるのです。 「今、自分は不安を感じているだけで危険な状態ではない」と自分に言い聞かせるのも有効です。
実際に、厚生労働省では下記呼吸方法をおすすめしています。
不安や緊張が強くなると、運動をしているわけでもないのに、「ハアハア」と息が上がってくることがあります。呼吸も浅く、速くなり、汗が出てきて心臓もドキドキ。つらいと思いますが、こんなときこそ意識して「深い呼吸」を心がけてみてください。
引用:厚生労働省 こころもメンテしよう
やり方は簡単。椅子に腰掛けている場合は、背筋を伸ばし軽く目を閉じ、おなかに手を当てます。立っている場合も、リラックスしておなかに手を当ててみましょう。
呼吸の基本は「ちゃんと吐く」ことから。まずは「いーち、にー、さーん」と頭の中で数えながら、ゆっくりと口から息を吐き出します。息を吐き出せたら、同じように3秒数えながら、今度は鼻から息を吸い込みます。これを5~10分くらいくりかえします。
息を吐くときにおなかがぺったんこに、息を入れたらおなかが膨らむ…。そう意識して呼吸すると、より深い呼吸ができるようになります。そう、これが「腹式呼吸」と呼ばれるものです。
途中で、「今日は宿題あったっけ?」などと、余計な考えが浮かぶこともあると思いますが、そんなときは気にせずさっと流して、また「いーち」から数え直しましょう。
このように事前に対処法を準備していれば、「発作が起きたらどうしよう」という不安が減ります。パニック障害の症状が出た時の対処法を練習しておきましょう。
症状別にパニック障害の対処法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
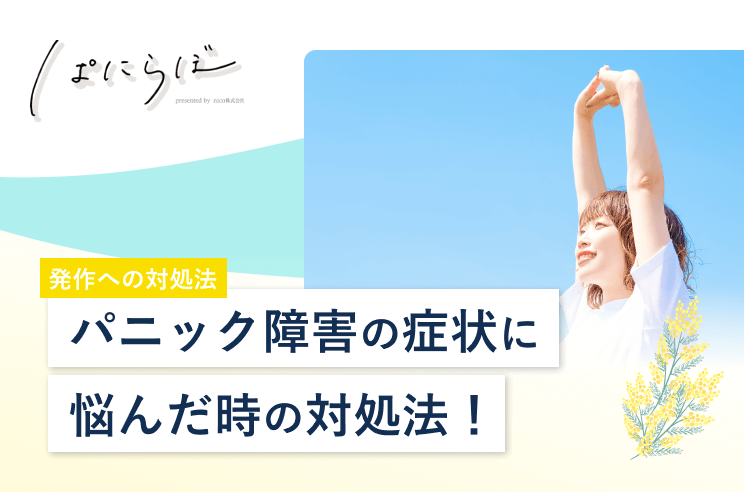
解消法5:安心グッズを持っていく
「これさえあれば大丈夫」と思える安心グッズを持ち歩くことで、不安を抑えられます。発作が起きたときに「すぐに対処できる手段がある」とパニックに陥りにくいです。
実際に、以下のアイテムを持っていると安心できます。
- ミントガム:口を動かすことで気が紛れる
- 飲み物:息苦しさや喉のフキを感じたときに使える
- アロマオイルやハンカチ:好きな香りでリラックスできる
- イヤホン:移動中の緊張を軽減する
実際に「にこっとプラス」の会員さんのなかには、イヤホンを持ち歩くことで落ち着ける方も多くいます。
「外出には必ずイヤホンを持ち歩いています。
引用:不安・パニック障害専門のオンラインサポートコミュニティ「nico+(にこっとプラス)」
バイラテラル音楽を聞くとスーッと落ち着きます。 」
「外出先で不安になったら急いでイヤホンをし、音楽を聞きます。またはイヤホンをするだけでも、外部の音が遮断され、落ち着く効果があると思います。」
引用:不安・パニック障害専門のオンラインサポートコミュニティ「nico+(にこっとプラス)」
どの安心グッズが合うのかは人それぞれですので、まずは試してみることをおすすめします。
上記を含め、持ち運びやすいパニック障害の人が安心できるものをより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

パニック障害を持つ人が外食に誘われた時の対処法


友人から誘われたのに外食に行けない…断るのがおっくう
遊んでいる途中でご飯を食べることになったが、外食はいやだ…
次のママ会、外でランチだけどどうしよう…
なかには、友人や知人から外食へ誘われた際に、どう対処すればいいのかわからない方もいますよね。
そこでここからは、パニック障害を持つ人が外食に誘われた時の対処法を、4つにまとめて紹介します。
対処法1:素直に症状を打ち明ける
信頼できる友人には、パニック障害を素直に打ち明けると安心します。症状を理解してもらうことで、パニック障害による心理的なプレッシャーを感じにくくなるのです。
パニック障害の症状を打ち明けるときは、シンプルに伝えることが大切です。詳しく話をすると負担が多く、不安が強まることがあります。
たとえば、「外食が苦手なことがあるんだけど」とシンプルに打ち明けることにより理解を得られるでしょう。
無理なく相手に伝えることが大切です。
対処法2:個室を提案する
外食の際は個室を提案することで、パニック障害の症状から落ち着いて食事ができます。提案の仕方は、シンプルに伝えることが大切です。
たとえば、「人が多い場所は緊張しやすいから、できれば個室がいいな」と伝えましょう。相手に嫌な思いをさせないように伝えることが大切です。
また、事前に個室のあるお店を調査し「ここに行きたい」と伝えることで自然に提案できます。
個室を提案するときは、相手に誤解を生まないように自然に提案しましょう。
対処法3:混みそうな時間は避ける
外食を誘われた時に、混みそうな時間を避けることによりパニック障害の不安を軽減できます。相手が迷わないように、具体的な時間を提案するとスムーズに会話が進みます。
たとえば、「いつでも大丈夫」より「平日のランチなら」と具体的に伝えることにより時間帯の指定が可能です。
また、空いてる時間に「みんなも快適に過ごせる」と理由を付け加えることで混みそうな時間帯を避けられます。
提案する時は、相手へのメリットも伝えると空いている時間帯での外食ができます。
対処法4:行き慣れた店を提案する
行き慣れたお店を選ぶことで安心感が増します。新しい場所や慣れない環境はパニック障害による不安の引き金になります。
たとえば、相手に提案する際「ここのお店の料理が美味しい」と伝えることで興味を惹けます。その結果、行き慣れたお店を自然に提案できるのです。
行き慣れたお店に行くことで、パニック障害による不安を軽減できるので相手に提案してみましょう。
パニック障害を持つ人が外食できるようになる訓練法
外食できるよう、次のステップに沿って訓練を重ねましょう。
「どのお店か」「誰と行くか」「どの席に座るか」をイメージする
店の雰囲気を確認し、実際に注文するイメージをする
テイクアウトを利用し、店員と少しだけ会話する
極力人がいない時間帯に外食する
信頼できる人と無理をせず外食をする
無理せず少しずつ滞在時間を伸ばしていく
まずは外食をイメージする所から始め、実際にお店の前まで行きましょう。慣れてきたら、テイクアウトや信頼できる人と一緒に外食をします。
外食に対する抵抗感が無くなってきたら、徐々に普段の外食に戻しましょう。無理をせずに、「途中で帰ってもいい」と考え気軽に訓練することが大切です。
パニック障害を持つ人が無理に外食する必要はない

パニック症状への恐怖から、外食ができないことで不安や焦りを感じている方も多いですよね。しかし大前提として、無理に外食を知る必要はありません。
大切なことは、「できないこと」に目を向けるのではなく「自分が安心できる選択」をとることです。外食できなくても、友人や家族と一緒に食事を楽しむ方法はあります。
また、焦って無理をすると不安が増し、症状が悪化するでしょう。「今は外食しなくてもいい」「無理せず自分のペースで進めばいい」と考えることが、心の負担を軽減します。
自分にとって安心できる環境を選ぶ、無理のない範囲で生活しましょう。
パニック障害を持つ方が自宅で外食を味わう方法
自宅で外食を味わう方法は2つあります。
- テイクアウトをする
- 自宅をお店のように装飾する
テイクアウトをすることにより外食している気分を味わえます。外食せずとも、ウーバーイーツなどのデリバリーやドライブスルーを活用することも可能です。
また、自宅をお店のように装飾することにより気分が上がります。外食できなくても、アイデア次第で友人や家族と一緒に食事を楽しむ方法はあるので工夫が大切です。
外食先のお店で症状が出た時はどうすればいい?
外食先のお店で症状が出た時は、以下の対処法をお試しください。
深呼吸をして落ち着く方法は、まず4秒かけて鼻から息を吸います。そして、7秒間息を止め、8秒かけてゆっくり口から息を吐きましょう。これを数回繰り返すことで副交感神経が働き心が落ち着くようになります。
症状が強くて動けなくなった場合、無理をせず店員に助けを求めましょう。体調不良は誰にでも起こることなので遠慮する必要はありません。
焦らず、ゆっくりと対処しましょう。
まとめ
パニック障害を持っている人は、無理して外食をする必要はありません。外食が難しい場合は、テイクアウトや自宅をお店のように装飾して外食気分を味わう手段もあります。
また、友人や知人からの外食の誘いに困った場合は本記事を参考にしてください。乗り越えようと焦るよりも、「今の自分にできる範囲で」楽しめる方法を選ぶことが大切です。
こちらの記事もおすすめ