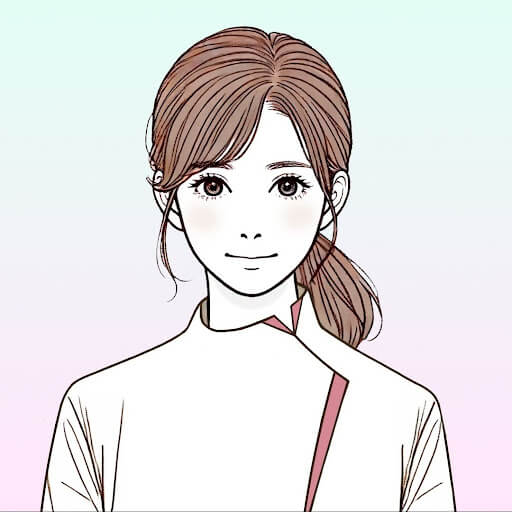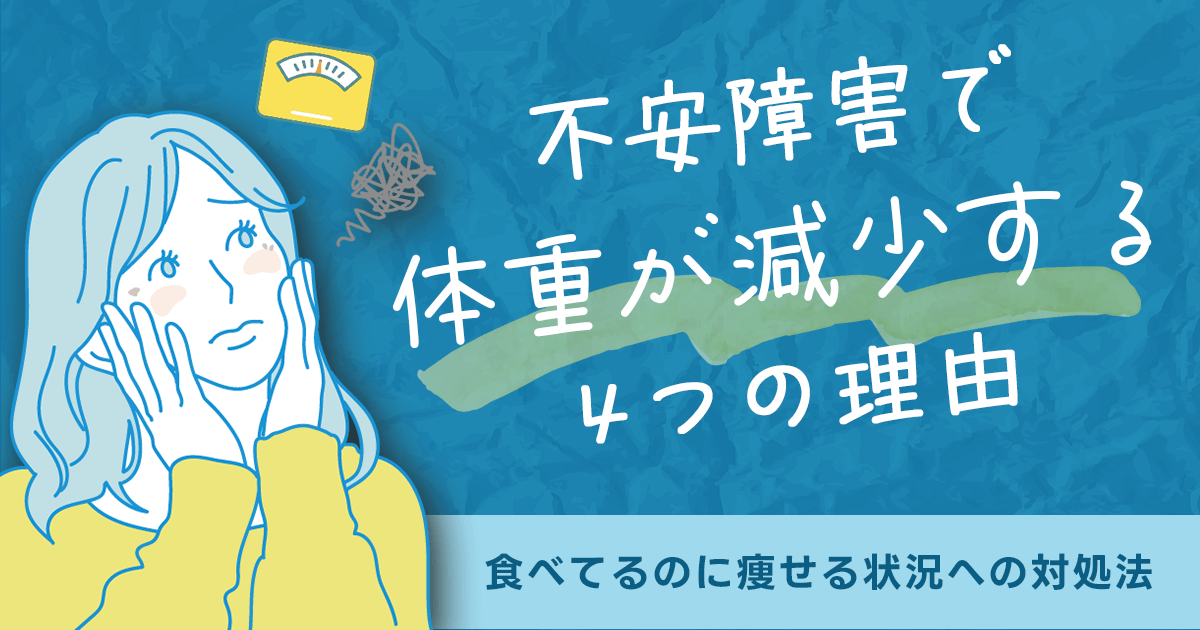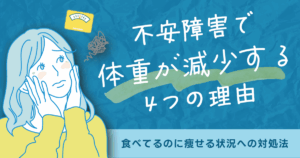この記事では食べてるのに痩せる状況への対処法も交え、不安障害で体重が減少する理由を解説します。
- 不安障害の体重減少は自律神経や消化機能の不調が考えられる
- 気になる体重減少には意識や生活習慣の改善で対処しよう
- 自力で対処できず生活に支障がある場合は受診しよう
なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。
「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。
「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。
「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。
本記事を音声で聴く
不安障害で体重は減少する?
結論、不安障害で体重が減少するケースはあります。詳しい理由は後述しますが、体重減少には不安による食欲不振や消化機能の低下、自律神経の乱れが影響しているためです。
しかし、痩せる程度には個人差があり、痩せる人もいますが太る人もいます。以降ではその理由やケースを詳しく解説します。
痩せる程度には個人差がある
不安障害による体重減少の程度には個人差があります。なぜなら、体質や基礎代謝、日々の運動量などが人によって異なるためです。
たとえば同じように食事量が減ったとして、Aさんは1~2kg、Bさんは5kg以上体重が落ちてしまうことがあります。
食べられないほどの強い不安を感じる人もいれば、食欲には影響が出ない人もいます。ストレスや不安の感じ方や反応の仕方も人それぞれで、体重変化の現れ方も異なるのです。
不安障害による体重減少は起こり得ますが、幅があるため、一律に語れるものではありません。
なかには体重が増え太る人も
痩せる方がいる一方、不安障害で体重が増加するケースもあります。前述したように、ストレスや不安に対する反応は人それぞれ異なり、体重増加する場合があるためです。
例として、甘いものやジャンクフードを食べることで不安をまぎらわせたり、気分を落ち着かせたりする人もいます。普段は節制していても、嫌な出来事をきっかけに過食に走ってしまうケースもあるのです。
実際に、不安障害で体重が増えたことを実感している人もいます。
「私は、双極性障害と不安障害です。
引用:Yahoo!知恵袋
鬱の抗うつの時は、20キロ痩せたり、
躁鬱のときは、10キロ太ったりします。
体重の幅は、30キロの中を
痩せたり、太ったりを繰り返しています。」
不安障害には、体重が減るだけでなく、増える場合があることも覚えておくべきです。
下の記事では不安障害で太る場合の詳細をまとめているため、参考にしてください。
→内部リンク:不安障害太る
不安障害で体重が減少する4つの理由
ここからは不安障害で体重が減少する理由を、4つにまとめて解説します。
なお、日常生活に潜む不安障害の原因をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。
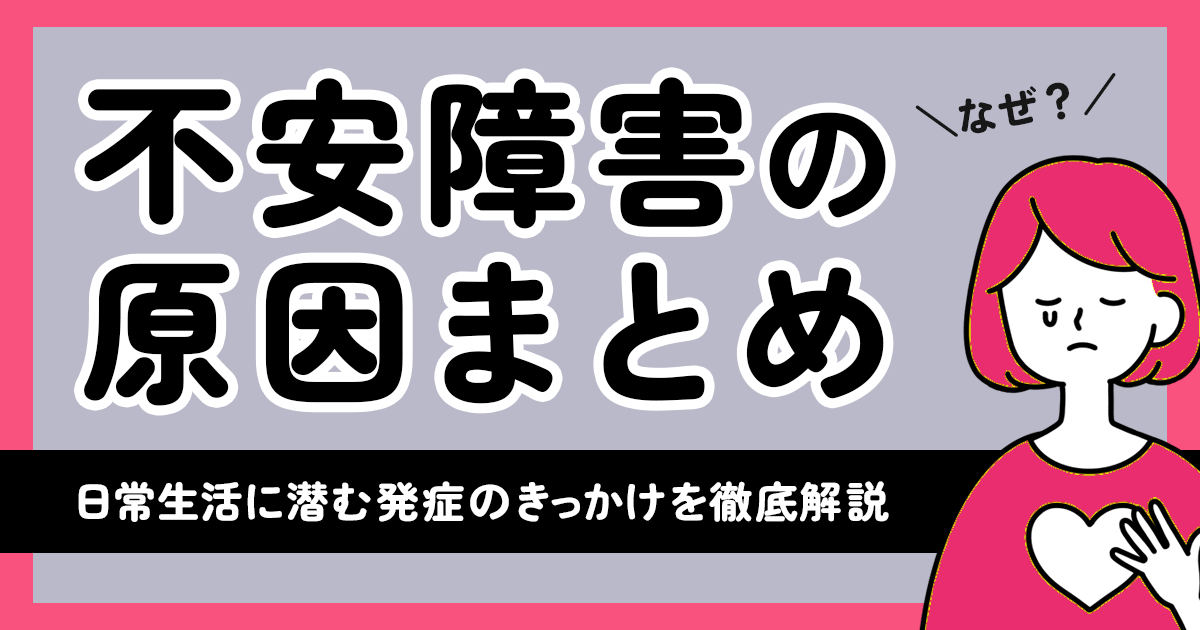
食欲が出ない
食欲が出ない点は、不安障害で体重が減少する大きな理由の1つです。強い不安やストレスにさらされることで自律神経が乱れ、食欲に影響するためです。
とくに継続した不安やストレスは脳の視床下部(ししょうかぶ)にも影響します。視床下部は、食欲や睡眠、体温調節など生命維持に重要な働きをする部分です。視床下部の機能が乱れると、食欲そのものが落ちやすくなります。
また、強い不安や緊張状態が続くと、胃腸の働きが鈍くなりがちです。食べ物を見ても食べたいと思えなかったり、口に入れてもなかなか飲み込めないという人もいます。
食欲低下が続くことで、結果的に体重が少しずつ減っていくのです。
ストレスによる吐き気や消化不良
ストレスによる吐き気や消化不良も、不安障害で体重が減少する理由の1つです。なぜなら、ストレスにより胃のむかつきや吐き気、胃痛などが起きやすくなるためです。
厚生労働省の「こころの耳」でもストレス反応として、胃痛や食欲低下、便秘などが報告されています。行動のストレス反応には飲酒や喫煙の増加もあげられており、消化器官への悪影響も懸念されるところです。
不安障害では、消化器の不調による食欲低下は避けては通れない問題です。
過剰なエネルギーの消費
過剰なエネルギーの消費も、不安障害で体重が減少する理由の1つです。強い緊張や不安が続くと交感神経が過活動を起こし、心拍数や血圧が上昇しエネルギー消費が進むためです。
とくにパニック発作や甲状腺機能亢進症を合併している場合、頻繁に動悸や発汗が起こるため、代謝が上がりやすいです。
『いつも通り暮らしているのに、なぜか体重が減っていく』場合は、見えない形で過剰なエネルギー消費が起きていないかを考える必要があります。
体重減少の理由にほかの疾患が隠れている可能性も考え、受診を検討してもいいでしょう。
防衛反応としての代謝更新が、体重の減少には大きく影響しています。
生活リズムの乱れ
生活リズムの乱れも、不安障害で体重が減少する理由の1つです。なぜなら、睡眠不足や慢性的な疲労で食事のタイミングを逃しやすくなり、食欲も低下しやすくなるためです。
以下のような暮らしは、生活リズムが乱れやすいです。
- 起床や就寝の時間が定まっていない
- 食事を食べたり食べなかったりする
- 早出や遅出、夜勤などがある仕事に就いている
食事の際に「面倒だし食べない」「お菓子だけでいいや」などが続くと、自然と体重は減少していきます。
不安障害があり、体重の減少で悩んでいる方は、生活のリズムが乱れていないか確認しましょう。
不安障害で体重が減少しているかを判断するには?
不安障害で体重が減少しているかは、下のチェックリストで判断しましょう。「はい」が多い場合、体重減少の原因は不安障害だと考えられます。
- 食事の量が減った自覚がある
- 食事に対する恐怖や不快感がある
- 最近、強い不安やストレスを感じている
- 動悸や息苦しさ、胃の不調を感じる
- 不安や体調不良が原因で日常生活に支障が出ている
上記はあくまで目安のため、より正確に判断したい方は医療機関を受診しましょう。なお、内科疾患や甲状腺疾患・代謝異常・がんなどを発症している可能性があるため、次の要素に当てはまる場合は内科・心療内科の受診をおすすめします。
- 急な体重減少(1ヶ月で3kg以上)
- 食べているのに痩せる
- 夜間発汗や微熱、強い疲労感などがある
不安障害による体重減少への対処法
ここからは不安障害による体重減少への対処法を、5つにまとめて解説します。不安障害による体重の減少には、心のケアと体のアプローチを両立することが必要です。
「増やす」より「減らさない」意識を持つ
増やすより減らさない意識をもつことは、不安障害による体重減少への有効的な対処法となります。なぜなら、体重を増やさないといけないという気持ちがプレッシャーになり、余計に不安障害を加速させる可能性があるためです。
一度にたくさん食べられない場合は、少量を1日5~6回に分けて食べることもおすすめです。ヨーグルトやスムージー、ゼリー飲料などは喉を通りやすいですよ。
「今日はゼリー1つ食べられたからOKにしよう」と、自分を褒め、自己肯定感を下げない工夫も必要です。
体重を減らさない意識をもつことで、不安障害の体重減少には備えられます。
効率よく栄養を摂る
効率よく栄養を摂ることも、不安障害による体重減少への有効的な対処法の1つです。なぜなら過不足ない栄養で自律神経が整い、健康的な身体作りにつながるためです。
下記に栄養が摂れる食事をまとめているため、参考にしてください。
| 栄養が摂れる食事 | バナナやおかゆ、うどんなど栄養価が高く消化にいいもの野菜スープ、プリンなど噛まずに食べられるもの |
| 栄養が摂れない食事 | 丼ものやパスタなど糖質ばかり摂るお菓子やジャンクフードをメインにする食事をゼリー飲料やエネルギーバーで済ませる |
『食べなければならない』に捉われず、極端な食事には注意しましょう。
消化に良い食品を選ぶと食事の負担は少ないです。効率よく栄養を摂れば、不安障害の体重減少にも備えられます。
栄養不足が不安障害に与える影響をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。
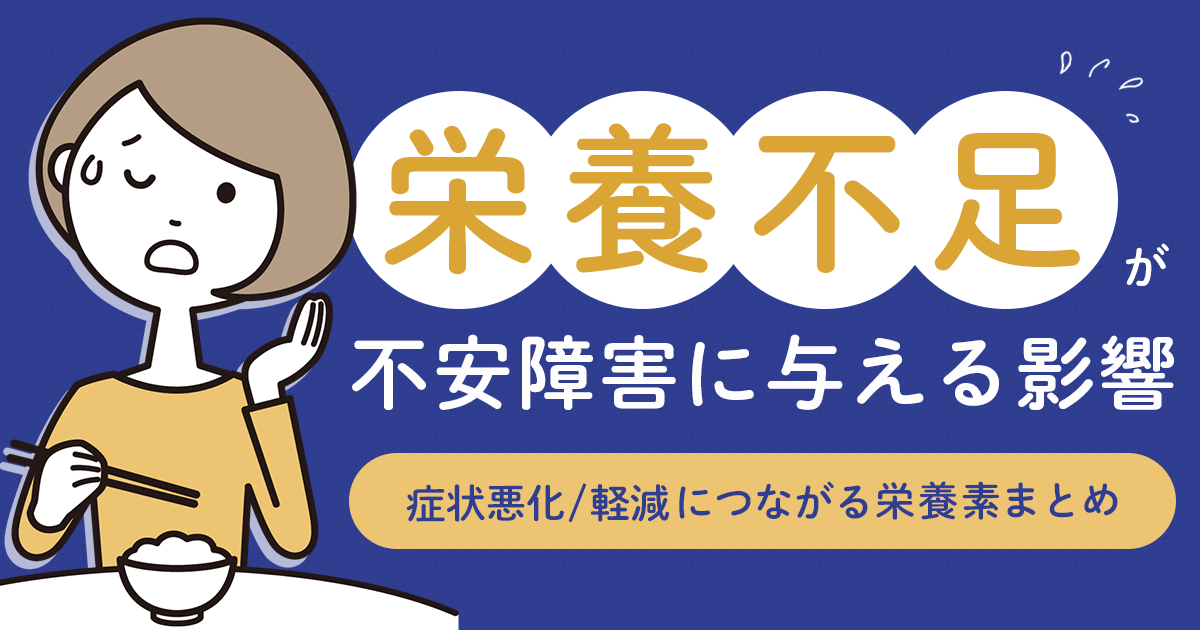
不安障害の症状を和らげるおすすめの飲み物を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

生活習慣を整える
生活習慣を整えることも、不安障害による体重減少への有効的な対処法の1つです。規則正しい生活で健康になり、未病や病の改善につながるためです。
たとえば、夜更かしや不規則な食事は交感神経を優位にしやすく、心身を緊張状態にします。消化機能や食欲が低下し、自然と体重が減ってしまうでしょう。
悪循環を断ち切るためには、起床や就寝時間を一定にし、バランスのよい食事と運動を取り入れましょう。スマホの時間やカフェインを減らし、リラックスできる時間を増やすと心身ともに安定しやすいです。
生活習慣を整えると、健康維持だけでなく、心の安定や自尊心の回復にもつながります。
なお、不安障害の方が日常生活で気をつけるべき行動を下記の記事でまとめているため参考にしてください。

メンタルケアに取り組む
メンタルケアに取り組むことも、不安障害による体重減少への有効的な対処法の1つです。なぜならストレスを軽減する手段を身につけていると、メンタルの回復や食欲低下の予防につながるためです。
たとえば不安が溜まるとセロトニンやノルアドレナリンなどの脳内の神経伝達物質が乱れ、食欲が低下しやすくなります。しかし、心の安定が保てると悪影響を少なくできるのです。
メンタルをケアする方法には、下記の手段があります。
- 好きなものを食べる
- 音楽を聴いて気分転換をする
- 睡眠を十分にとる
- 趣味を楽しむ
- 認知行動療法(CBT)に取り組む(※1)
- 呼吸法(※2)に取り組む
個人の性格や価値観によって、それぞれの効果は異なります。どの方法が一番気分を保ちやすいかを知っておくと、不安を感じた際にすぐに対処できるでしょう。
心の安定を保つ方法の1つとしてぬいぐるみの利用を下記で解説しているため、参考にしてみてください。

周囲の助けを借りる
周囲の助けを借りることも、不安障害による体重減少への有効的な対処法になりえます。理由として、不安障害が基礎にあると、思考や行動の偏りによって自力での対処が難しくなるためです。
不安障害は外見から見てもわかりにくいため、理解されないと感じている人もいるかもしれません。ただの体調不良だと思われてしまうこともあるでしょう。
「食べられなくてつらいこと」や「不安障害で悩んでいること」を相談すると、心の負担も軽くなります。
相談する相手には、同じ症状を持つ人や理解が得られそうな人など、距離が近く信頼できる人物を選びましょう。不安障害に悩む方のオンラインコミュニティや、患者会などだとすぐに受け入れられるはずです。
下の記事では、不安障害が理解されない理由や対処について詳しくまとめているため参考にしてください。

まとめ
本記事では、不安障害による体重減少の理由と、受診すべきサインについて解説しました。体重が減っていると感じたら、まずは生活リズムや食習慣を見直し、周囲や専門家の助けを借りることが大切です。
必要以上に体重にこだわらず、心身が健やかに保てる食生活を続けることが、回復への第一歩です。体調や気持ちに不安があるときは、早めに医療機関へ相談しましょう。
食事も心のケアも、無理なく続けていくことが大切です。不安障害と向き合いながら、自分のペースで健康を取り戻していきましょう。