体重が増え続ける現状への対処法も交え、不安障害で太る理由を解説します。
- 不安障害が原因で太るケースもある
- ストレスによる過食や薬の副作用、運動不足などは太る原因である
- 不安障害で太ってきたら過食するきっかけは何かを特定する
なお、周囲にパニック障害の悩みを相談できず、おひとりで悩まれている方は不安・パニック障害に悩む7万人以上の方が参考にした、不安パニック専門のオンラインサポートコミュニティ「nicot+(にこっとプラス)」をご活用ください。
「にこっとプラス」では、次のようにオンライン上で参加者同士が症状への悩みや対処法といった情報を気軽に交換できます。
「気持ちがわかってもらえるか不安…」といった方でも、同じパニック症状に悩む参加者同士であれば、気負いすることなく悩みや不安を打ち明けられますよ。
「どんなところなんだろう?」と気になる方は、下のボタンから詳細をご確認ください。
太るのは不安障害が原因?
結論、不安障害が原因で体重が増加するケースはあります。強い不安やストレスは心の状態だけでなく、食行動や身体にも影響を及ぼすからです。
たとえば、不安を紛らわすために無意識に食べたり、治療で服用する薬の副作用が関係したりします。外出する気力がなくなることで運動量が減るのも、体重増加につながる要因の1つです。
不安障害と体重増加にはいくつかの関連性が考えられます。次の章では、なぜ不安障害で太ることがあるのか、具体的な理由を詳しく解説します。
不安障害で太る5つの理由
ここからは不安障害で太る理由を、5つにまとめて紹介します。
理由1:ストレスによる過食
ストレスによる過食は、不安障害で太る理由の1つです。
不安や緊張が続くと心のバランスを保とうとして、食べる行為で落ち着こうとします。そのため、脳が「不安になっても食べれば楽になる」と学習してしまい、食べる行動が習慣化しやすいのです。
これは、お腹が空いているかどうかとは関係なく湧きおこる食欲です。とくに、甘いものや脂質の多い食べ物を無意識に求めてしまう傾向があります。
その結果、摂取カロリーが消費カロリーを上回り、体重増加につながるのです。栄養不足が不安障害に与える影響を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。
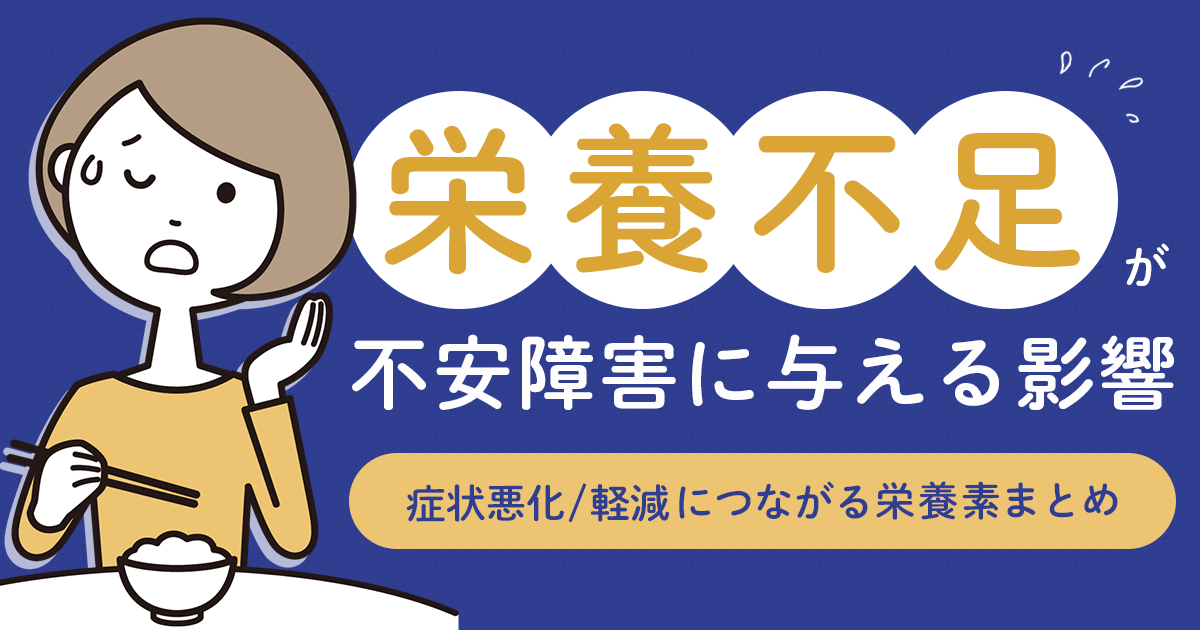
理由2:薬の副作用
不安障害で太る原因には、薬の副作用があります。
不安障害の治療で用いられる薬には、副作用として体重増加が報告されているものがあります。
代表的な薬は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)という抗うつ薬です。SSRIは不安を和らげる効果が期待できる一方で、長期的に服用すると代謝の変化や食欲の増進が現れます。
また、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、眠気やだるさを引きおこす場合があります。その結果、日中の活動量が減り、消費カロリーが低下して間接的に体重が増えやすくなるのです。
薬の副作用で体重増加が疑われるときは、必ず処方している医師に相談しましょう。不安障害における薬の副作用で太るケース背景や事例をより詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてください。

理由3:運動不足
運動不足は不安障害で太る理由の1つです。
不安感が強いと、身体を動かす意欲が低下します。「外出が怖い」「電車や人混みが不安」などの症状により、自宅で過ごす時間が長くなるためです。家にこもりがちになると、通勤や買い物などで身体を動かす機会が失われ、1日の消費カロリーが減少します。
活動量が減ると筋肉も衰えやすく、基礎代謝も低下します。基礎代謝が落ちると、以前と同じ量の食事を摂っていても、エネルギーが消費されにくく脂肪として蓄積されやすくなるのです。
「不安だから動けない」という状況が、体重増加の悪循環につながります。不安障害の治療における運動の効果を詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
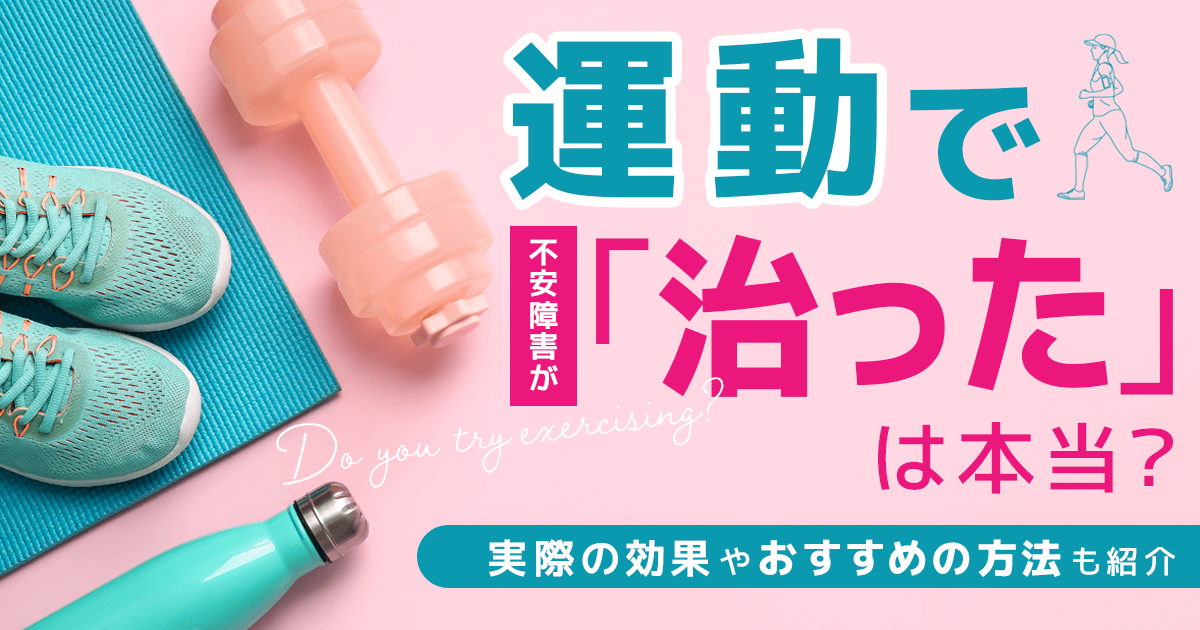
理由4:食欲ホルモンの乱れ
食欲ホルモンの乱れは、不安障害で太る原因です。
不安障害は睡眠の質を低下させることがあり、睡眠不足が食欲をコントロールするホルモンバランスの乱れを引き起こします。
スタンフォード大学の研究によると、睡眠時間が5時間の人は8時間の人に比べて、食欲を増やすホルモンである「グレリン」の血中濃度が14.9%高く、食欲を抑えるホルモン「レプチン」が15.5%低いという結果が報告されています。
睡眠不足の状態では食欲が増し、満腹感を得にくくなるのです。その結果、夜中に目が覚めて何かをつまんだり、日中に高カロリーなものを食べたくなったりと、体重増加につながります。
理由5:自己肯定感の低下
自己肯定感の低下は、不安障害で太る理由の1つです。
不安障害の方は、物事をネガティブに捉えやすい傾向があります。体重が増えることで体型が変化し、自己肯定感が下がるとさらに不安を強めてしまう悪循環となります。
鏡に映る自分の姿や、きつくなった服を目の当たりにするたびに「自分はだめだ」「自己管理もできない」と自分を責めてしまうでしょう。「太っていることを他人にどう思われるだろう」という他者からの視線への恐怖が、不安の種になるケースもあります。
自己評価が下がると、過食や引きこもりにつながりかねません。自分を否定する気持ちが不安を増幅させ、不安を解消するためにまた食べるというサイクルに陥るのです。
不安障害による体重増加を放置するとどうなるか
不安障害による体重増加を放置すると体調不良や症状悪化などを引き起こし、次のような悪循環につながる可能性があります。
- 体重増加が進む
- 自己肯定感が下がる
- 社会的に孤立する
- 精神疾患を併発・重症化する
- 身体的健康が深刻に悪化する
まず、過食や運動不足が続くと肥満が進行し、体力の低下を実感しはじめます。
次に、体型の変化は自己肯定感を低下させます。鏡を見るたびに「自分が嫌い」と感じ、食べ過ぎた後には自己嫌悪に陥るようになるのです。
さらに自己嫌悪が進行すると「太った自分を誰にも見られたくない」という思いから、仕事や学校を休みがちになり、社会的に孤立してしまう恐れがあります。
こうした状況は不安障害だけでなく、うつ病や摂食障害などの他の精神疾患を併発するリスクを高めます。
最終的には、肥満が引きおこす糖尿病や高血圧などの生活習慣病と精神的な不調が重なり、心身ともに健康を損なう事態も考えられるのです。
不安障害が原因で太ったかを判断するには?
不安障害が原因で太ったかを判断する際は、下記の5つに当てはまるかを確認しましょう。当てはまる項目が多いほど、不安障害が体重増加に影響していると考えられます。
| 判断ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 体重増加と不安症状の時期が重なっているか? | 体重が増え始めた時期と、不安やパニック発作 などの症状が強くなった時期はいつか |
| 食べる量やタイミングが変化したか? | 不安を感じたとき、心を落ち着かせるために 甘いものや炭水化物を無性に食べたくなるか |
| 薬の服用による副作用の可能性はあるか? | 処方されている薬の 副作用に体重増加があるか |
| 活動量・運動量が以前より減っていないか? | 不安から外出を控えたり、 家にいる時間が増えたりした結果、 1日の消費カロリーが減っているか |
| 体重増加が生活習慣によるものか? | 加齢による基礎代謝の低下、 食生活の好みなど考えられる原因はあるか |
| 不安が強くなってから体重が増えたか? | 不安やストレスが強くなった時期と、 体重が増え始めた時期が重なっていないか |
| 食べることで気持ちを落ち着かせているか? | 不安やイライラを解消するため、 お腹が空いていなくても無意識に食べていないか |
| 処方薬を飲み始めてから太ったか? | 薬の服用を開始したタイミングを境に、 食欲が増したり体重が増えやすくなったりしていないか |
| 運動量が減っていないか? | 不安感から外出の機会が減り、 日常生活での活動量が以前より低下していないか |
| 睡眠が浅くなり、夜中に食べることが増えたか? | 寝つきが悪い、夜中に目が覚めるなど 睡眠の質が下がっていないか |
正確な判断には医師の診察が欠かせません。もし当てはまる項目が多いときは、心療内科や精神科、内科に相談しましょう。
不安障害で太る現状への対処法
ここからは不安障害で太る現状への対処法を、4つにまとめて紹介します。
1.過食の引き金(トリガー)を特定する
はじめに、過食の引き金(トリガー)を把握しましょう。いつ、どんな気持ちのときに食べ過ぎているかを客観的に知ると、無意識の過食を防ぎやすくなります。
具体的な方法として、次の項目を書いて簡単な食事日記をつけてみましょう。
- 時間
- 場所
- 気分(不安、イライラ、退屈など)
スマホのアプリやノートなど、試しやすい方法でかまいません。記録を続けると「仕事で嫌なことがあると、帰宅後にお菓子をたくさん食べてしまう」「夜に1人でいると不安になり、つい冷蔵庫を開けてしまう」など、自分の行動パターンが見えてきます。
記録の目的は、自分の感情と食欲の関係を理解するためです。引き金がわかれば、次はその状況を避けたり、別の行動に置き換えたりする対策を立てやすくなります。
不安障害の原因を詳しく知りたい方は下の記事を参考にしてください。
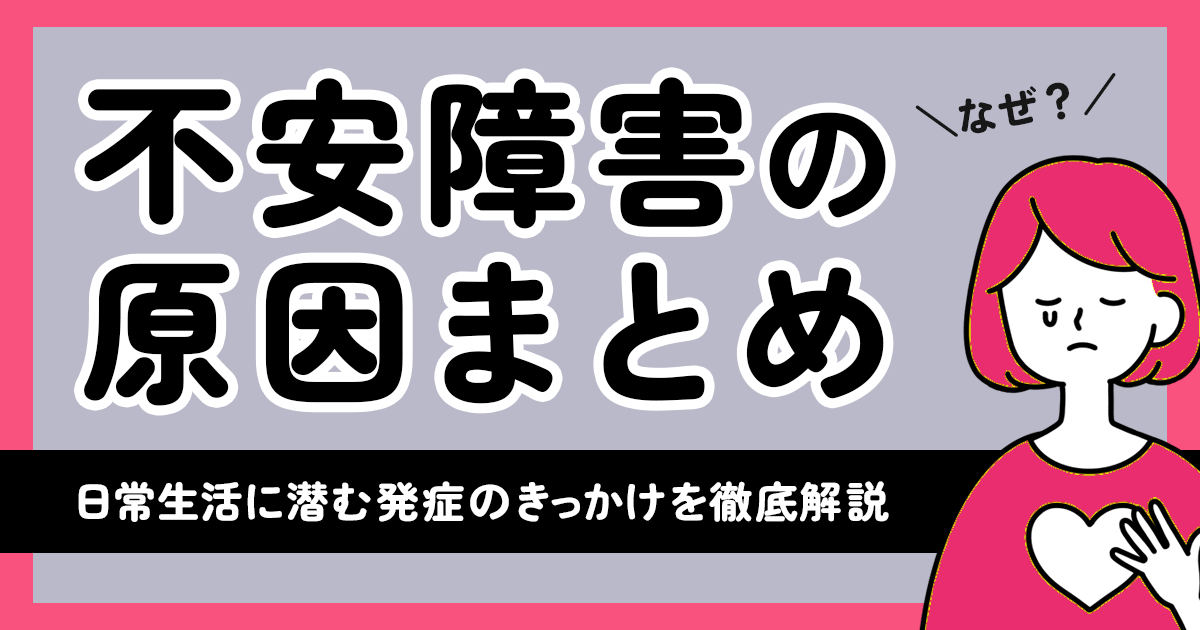
2.食事以外で不安を落ち着かせる方法を作る
食事以外で不安を落ち着かせる方法を作ることは、太る現状に有効です。
ヨガや瞑想などのリラクゼーション法は心拍数や血圧を下げ、心身を落ち着かせるのに役立ちます。たとえば、ゆっくりと息を吸って長く吐き出す深呼吸も、いつでもどこでも実践できる手軽な方法です。
また、アロマを焚いたり温かいハーブティーを飲んだりして「五感」に働きかける習慣もおすすめです。心地よい香りは嗅覚を、温かい飲み物は触覚と味覚を刺激し、不安から意識をそらす手助けになります。
不安を感じたときに「食べる」以外の選択肢を作ることが大切です。
不安障害の過ごし方を詳しく知りたい方は下の記事を参考にしてください。

3.服用薬を医師と再考する
体重の増加を抑えるためには、服用薬を医師と再考しましょう。
いつからどのくらい体重が増えたのか、食生活や運動量に変化はあるかなど、具体的な情報を伝えられると、医師も判断しやすくなります。
処方された薬の副作用により体重が増加しているか判断できなくても、自己判断で服用を中止するのは避けてください。症状が悪化したり離脱症状が出たりする危険性があるためです。
医師に相談するときは、次のように尋ねてみましょう。
- 「この薬を飲み始めてから体重が増えたのですが、副作用の可能性はありますか?」
- 「もし体重増加が副作用なら、生活で気をつけることはありますか?」
医師は、症状のコントロールと副作用のバランスを総合的に判断します。その結果、薬の量を調整したり、体重に影響の少ない別の薬への変更を検討したりしてくれます。まずは体重が増えるという悩みを率直に伝えてみましょう。
4.小さな運動から習慣化する
体重が増え続けているときは、小さな運動から習慣化しましょう。
不安障害を抱えているときに「ジムに通い本格的に運動する」という目標を立てるのは、ハードルが高く感じます。
おすすめは、自宅でできるストレッチやラジオ体操です。YouTubeで検索すれば、5分程度でできる簡単なものが見つかります。朝起きたときや気分が落ち込んだときに試すと、心身が軽くなるのを感じられるでしょう。
また、天気の良い日に5分だけ近所を散歩してみるのも気分転換になります。他にもエレベーターではなく階段を使う、1駅手前で降りて歩くなど、日常生活の活動量を増やす意識も有効です。
運動で不安障害が治るかを詳しく知りたい方は下の記事を参考にしてください。
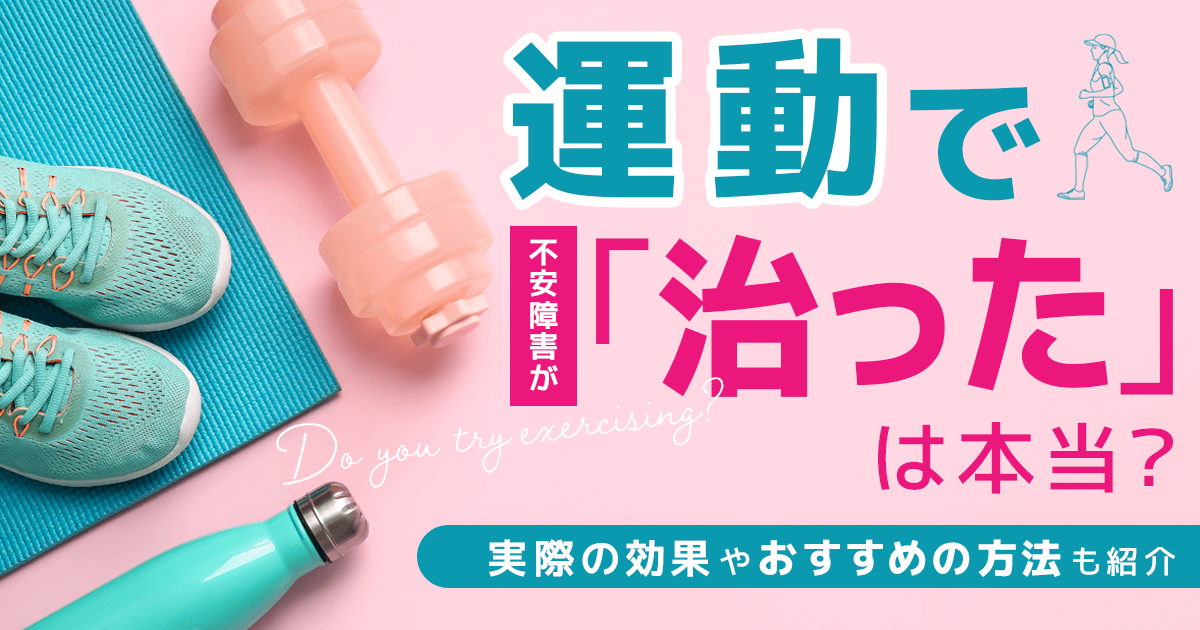
まとめ
不安障害と体重増加の関係は、ストレスによる過食や薬の副作用などさまざまな要因が関係します。体重増加を放置すると、心と身体の両面で健康を損なう悪循環に陥る可能性があります。
もし体重の増加に悩んでいたら、まずは原因がどこにあるのかを客観的に振り返りましょう。そして、過食の引き金を特定したり、食事以外のリラックス法を見つけたりして、できることから1つずつ試してみてください。
薬の副作用が疑われるときや、自分だけで対処するのが難しいときは、1人で抱え込まず医師に相談してください。適切なサポートを得ながら、少しずつ体重を減らしていきましょう。
こちらの記事もおすすめ






